
|
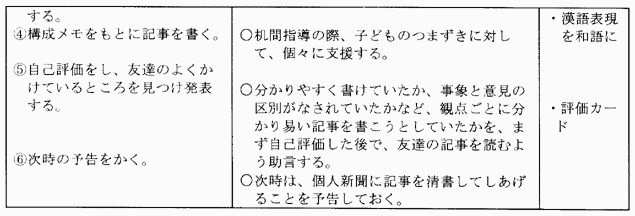
4 成果と課題
(1)子どもたちの表れについて
環境新聞づくりの取り組みをきっかけに、うれしいことに日々の生活の中から見つけた観察カードの記録や昼休みに虫取りや木登りなどに熱中する子どもたちが、増えたことがあげられます。
また、絶滅しそうな山野草、食べられる木の実、変わった名前のついている樹木などのいわれを調べ、そのことを記事に載せることで、周りの環境の変化に目を向ける子どもたちが育ってきました。
さらに、図工の教科とも関連させながら、「版画カレンダー作り」に取り組んだところ、「横戸の森」をテーマとして版画作りに取り組んだり、広報新聞にも学校林で見つけた話題を取り上げるなど、全校的な広がりに発展することができました。
ちょうどこの時期に、学級PTA活動があり、そこでも親子で「木のシルエット」を手掛かりに、樹木の名前探しを楽しむネイチャーゲームをしました。みんなの感じ取った体験を語り合う「わかちあいの時間」を持つことで、自然と一体になり、鳥や風の音を無心になって聞く貴重な体験をするといった自然との付き合い方があることを、大人も子どもも感じ取ってくれたひとときでした。
(2)記事の内容から
個性的な内容の記事が書けている子どもは、学校林をいつも散歩している人のインタビュー記事を入れたり、遊んだときの体験を生き生きと綴ったりしていました。
この横戸小の地域を見つめ直十素材として「学校林の新聞記事を書く」という活動は、5年生の国語や社会や図工といった教科間の横のつながりをつけて、同じ時期に実施した
ことでより効果をあげられたことが、この実践から分かってきました。
また、幻の野草を発見させる原動力になったのも、「観察カード」を書く活動を年間を通してやっていたからだと思います。そして、自分で発見した喜びを言葉で知らせていくコミュニケーション能力をきちんと育てていくことは、子どもの内発的なエネルギーとして持続させていく上で、とても重要なことの一つだということに気づきました。つまり、環境教育と表現力を育てていくこととは、全く別物ではないということだと思います。即ち、「新聞作り」という書く活動を通じて、体験活動の見直しを迫られ、より観察能力をとぎすませていく力をつけることになるからであります。
そこで、今後さらに環境教育とコミュニケーション能力(表現力)をつけていくこととのかかわりについて学んでいきたいと思っています。
(3)ネイチャーゲームの取り組みの効用について
学活時間を使っての学校林でのネイチャーゲームの取り組みについては、子どもたちにとっては、「遊びの延長」という感覚でしたが、自然の中での体験は、子どもの感性を豊
前ページ 目次へ 次ページ
|

|